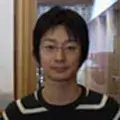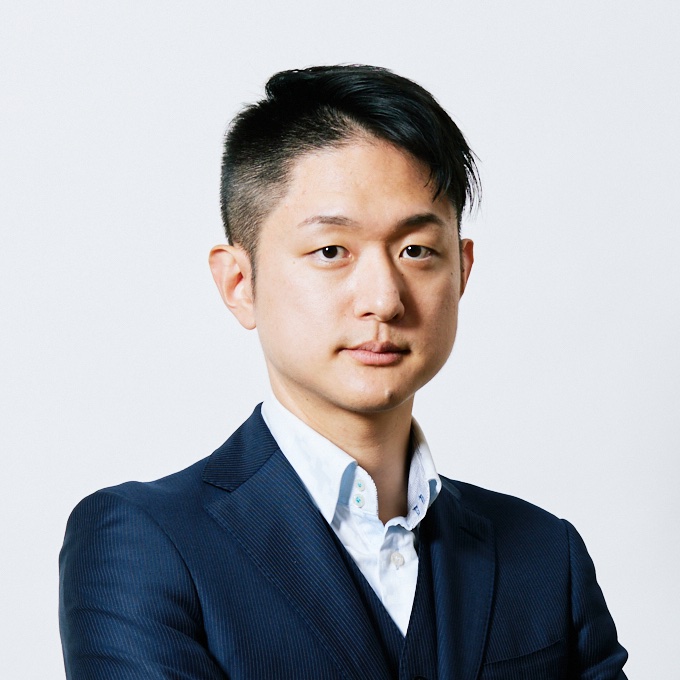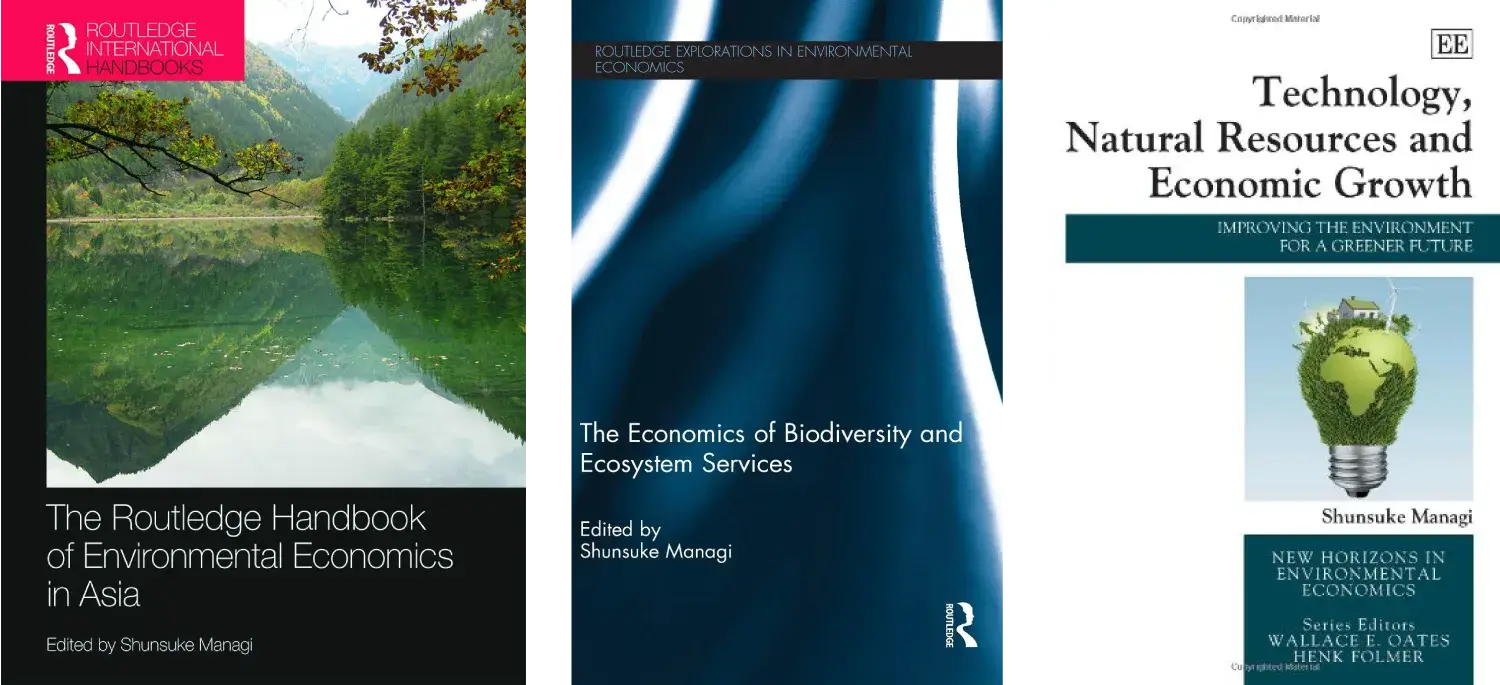持続可能性の、その先へ。

地上の太陽・核融合の実現による
持続可能なエネルギーシステムの実現

都市構造と交通システムの変化がもたらす
社会的影響の分析

衛星データに基づいた
自然・人・インフラの多面分析
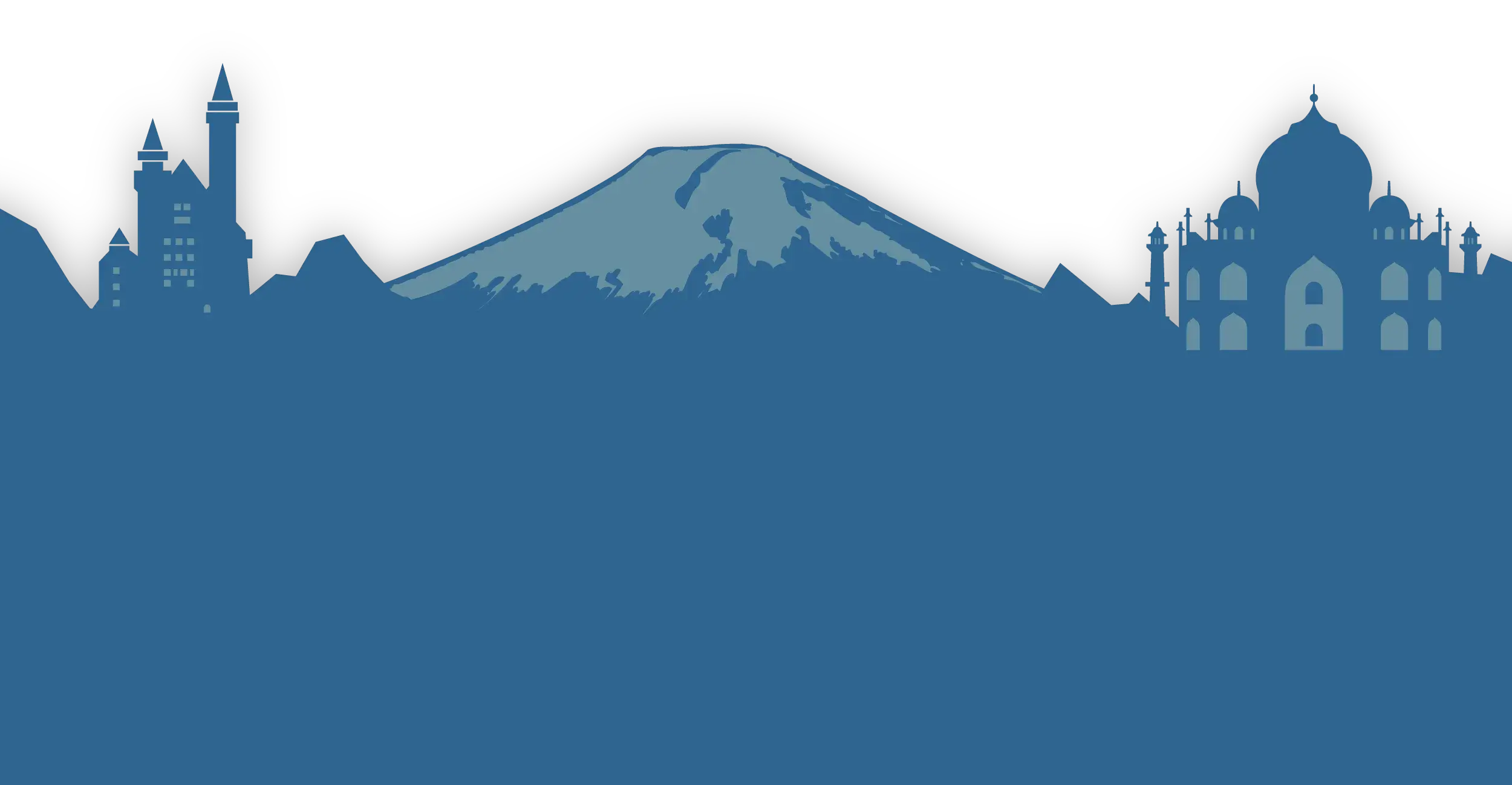
新国富指標の活用:
地域の豊かさの測定と持続可能性の評価

主観的幸福度に関する
大規模データベースの構築と活用

人口減少社会における
持続的発展社会に関する分析
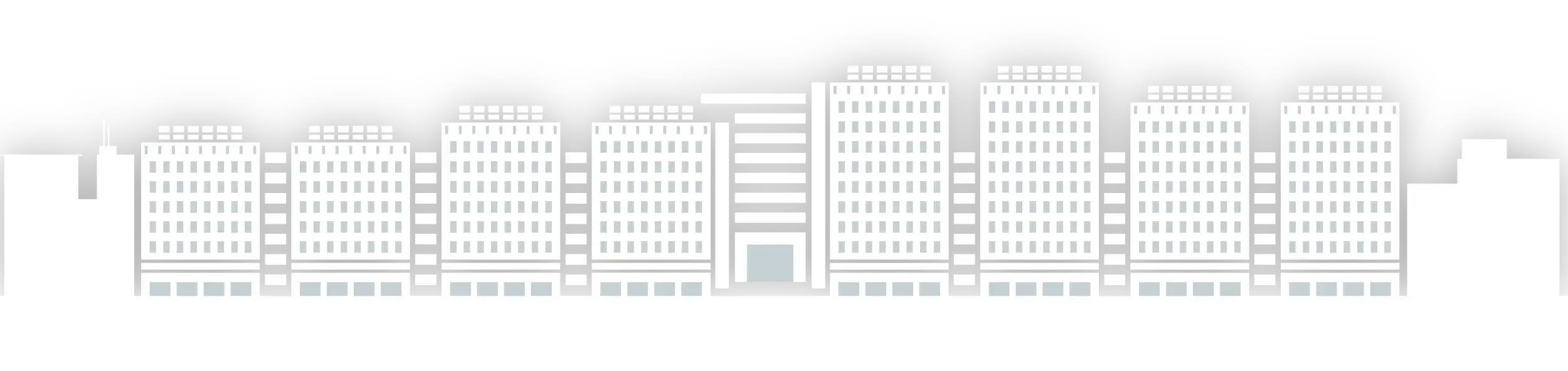


 Project
プロジェクト
Project
プロジェクト
-
Inclusive Wealth Report 2018 (IWR 2018)
-
新国富の活用:地域の豊かさの測定と持続可能性の評価
-
人口減少社会における、経済への外的ショックを踏まえた持続的発展社会に関する分析
-
主観的幸福度に関する大規模データベースの構築と活用
-
都市構造と交通システムの変化がもたらす社会的影響の分析
-
衛星データに基づいた自然・人・インフラの多面分析
-

地上の太陽・核融合の実現による持続可能なエネルギーシステムの実現